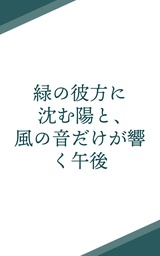「あまりにも価値がない。俺という存在には価値がないし、価値を生み出すこと自体ができないのだ」
高橋直人は、どこにでもいる普通のサラリーマンだった。東京の中堅メーカーに勤めて15年、営業職として日々ノルマに追われ、上司や取引先の機嫌を伺う生活。仕事に打ち込むことで得られる達成感も、家族を支えるという明確な目的もないまま、ただ「働く」という行為そのものが日常の習慣となっていた。高橋が初めて違和感を覚えたのは、40歳を迎えた年だった。社内では後輩たちが成長し、抜擢される姿を目の当たりにしながら、自分の存在が平凡で無意味に思えて仕方なかった。家庭でも同様だった。妻との会話は必要最低限に留まり、娘は反抗期を迎え父親を避けるようになった。居場所のない感覚が高橋を覆っていた。
ある日、部署の業績不振を理由に、上司から異動の内示が告げられた。それは自分のキャリアにおいて「左遷」に近い配置転換だった。高橋は、自分の人生が徐々に沈みゆく夕陽のように薄暗く感じられ、このまま働き続けることに意味があるのか考え始めた。
一通のメールから始まった異国への旅。そんな折、高橋の元に大学時代の友人、鈴木からメールが届いた。鈴木は5年前に会社を辞め、現在はベトナムのホイアンで小さなカフェを経営しているという。そのメールには、カフェの写真や現地の景色、そして短い一文が添えられていた。
「もし息苦しいなら、ここに来ればいい。風はいつも心地いいよ。」
鈴木からの軽い誘いだった。しかしその言葉は、高橋の胸に意外なほど深く響いた。日本での日常に飽き切っていた彼は、何かに背中を押されるように、会社に長期休暇を申し出た。そしてひとまずベトナムに行ってみることを決めた。
ホイアンに降り立った高橋を待っていたのは、湿り気のある温かい風と、赤褐色の瓦屋根が並ぶ穏やかな町だった。街路樹の間を縫うように走るバイク、川沿いの市場から漂うスパイスの香り、そして夕暮れになると現れる無数のランタンが灯る街並み。高橋はその非日常的な光景に、強い衝撃を受けた。友人の鈴木のカフェは、観光客が多く訪れる通りの一角にあった。木造の古い建物を改装したその店は、手作り感のある家具とベトナムらしい装飾品に彩られており、落ち着いた雰囲気を醸し出していた。高橋は鈴木の提案で、カフェの簡単な手伝いをすることになった。料理を運び、片付けをし、時折観光客の相手をする程度の仕事だったが、彼にとっては新鮮だった。
日本では常に「効率」や「成果」を求められてきた高橋だったが、ここではそのようなプレッシャーが存在しない。仕事を終えれば、バイクで田舎道を走ったり、近くのビーチで夕陽を眺めたりする日々が続いた。その単純で穏やかな生活は、高橋に忘れかけていた「生きている感覚」を取り戻させた。
カフェの仕事を通じて、高橋はベトナム人家族と交流する機会を得た。市場で野菜を売るフォンという女性とその子供たちは、貧しいながらも明るく温かい人々だった。高橋は彼女の家を訪れるようになり、質素な家で一緒に食事をするうちに、彼らの生き方に感銘を受けた。フォンは笑いながらこう語った。
「お金はないけど、家族がいれば幸せ。それだけで十分だよ。」
彼女の言葉は、高橋が日本で感じていた「欠けた何か」を埋める手がかりを示していた。高橋は自分が求めていたのは成功や地位ではなく、心の繋がりや人間らしい生き方だったのではないかと気づき始めた。滞在が3ヶ月を過ぎたころ、高橋は少しずつ自分自身を取り戻していった。早朝の川沿いを散歩しながら、自分のこれまでの人生を振り返ることが増えた。家族のために働くという名目で、実際には仕事に逃げ込み、家庭を疎かにしてきた自分。周囲に認められることばかりを追い求め、心の中で本当に大切なものを見失っていたことに気づいた。
ある日、高橋は鈴木にこう切り出した。
「俺、ここでしばらく暮らしてみようと思う。」
鈴木は微笑みながら答えた。
「いいじゃないか。きっとお前に合ってる。」
新しい生き方だ。それから高橋は日本に帰国せず、ホイアンで新しい生活を始めた。現地の人々に教わりながら農作業を手伝い、土を触る生活を楽しむようになった。忙しさや効率を追い求めることのないその暮らしは、彼にとってまさに解放だった。
ベトナムでの日々を通じて、高橋は自分の生き方を再定義した。そして、日本にいる家族との距離を取り戻すべく、少しずつ連絡を取るようになった。彼の人生にとって「目的」という言葉の意味は変わり、ただ幸せを感じられる瞬間を大切にすることこそが、生きる意義なのだと信じるようになった。ランタンが灯る穏やかな夜、田舎道を歩きながら、高橋は自分の中に残る欠片がようやく一つに繋がったような気がした。そして、その穏やかな日々が続く限り、自分はそれでいいのだと思えたのだった。
0
0
0
みんなのコメント
コメントはありません。