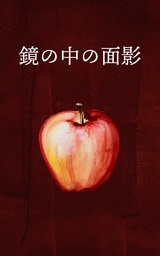ウルフリーは、文芸を愛するアマチュア・プロ作家のための、純文学、大衆小説、エッセイ、論考、詩の投稿サイトです。
「静かな日常が流れていく」
佐藤遥、32歳。彼女は小さな美容院で働く美容師だ。この美容院は、駅から少し離れた住宅街の一角にあり、派手さこそないが、近隣の住民に愛される憩いの場となっていた。遥は美容師として15年のキャリアを持ち、確かな技術と誠実な接客で多くの常連客を抱えている。どんなに忙しくても、手元の動きは正確で、客の希望を汲み取りながら、いつも最善を尽くす。その姿勢から「佐藤さんに任せれば間違いない」と評判だった。
だが、彼女の私生活は驚くほど平穏で、特筆すべき事件もなく過ぎていた。家と職場を往復する毎日。恋愛にも積極的ではなく、「今は仕事が忙しいから」と自分に言い聞かせ、深く考えないようにしていた。
ある日、遥のもとに一人の新規客が現れた。その男性は、西村慎也と名乗り、柔らかな物腰と落ち着いた雰囲気を持つ40代半ばの人物だった。
「カットをお願いできますか?」
そう言って座った西村の顔を見て、遥は息を呑んだ。
「もしかして……慎也さん?」
遥がその名を口にした瞬間、西村も驚いたように顔を上げた。
「佐藤……遥? 高校のときの?」
それは15年ぶりの再会だった。高校時代、遥は慎也と同じバスケットボール部のマネージャーをしており、慎也はチームのエースだった。互いに特別な感情を抱いていたが、告白することもなく、卒業と同時に別々の道を歩んでいた。
「懐かしいね。まさかこんなところで再会するなんて。」
慎也は微笑みながら言ったが、彼の表情には少しだけ影が差しているように見えた。その理由を尋ねることはできず、遥はただ髪を切る作業に集中した。それから慎也は定期的に遥の美容院を訪れるようになった。彼の話によれば、大学卒業後に外資系企業に就職し、現在は地方の関連会社で管理職を務めているという。仕事のストレスは多いものの、充実した日々を送っているようだった。
一方で、彼の左手薬指には指輪がなかった。遥はそれに気づきながらも、何も尋ねなかった。
「どうして離婚したんだろう?」
そんな思いが頭をよぎるたび、自分の感情が揺さぶられるのを感じた。高校時代の淡い恋心が、再び胸の中で芽生えつつあったからだ。
ある日の夜、慎也が美容院を訪れたとき、店には他に客がいなかった。カットが終わり、慎也が席を立とうとしたとき、遥が意を決して口を開いた。
「慎也さん、少しだけ話してもいいですか?」
慎也は驚いたようだったが、静かに頷いた。
「高校のとき、私はずっと慎也さんのことが好きでした。でも、それを伝える勇気がなかった。だから、卒業してからもずっと後悔してたんです。」
遥の言葉に慎也は目を見開いた。そして、少し間を置いて口を開いた。
「……遥、俺も同じ気持ちだったよ。でも、俺はあの頃、自分に自信がなかった。大学に行って、いい会社に就職して、それからじゃないと君にふさわしくないと思ってた。」
慎也の声は震えていた。
「だけど、俺はその間に違う道を選んでしまった。それが正しかったのかどうか、今でも分からない。」
彼の言葉に、遥はただ頷いた。それ以上、何も言うことができなかった。
それからしばらく、慎也は美容院に来なくなった。遥は彼のことを思い出すたびに胸が痛んだが、無理に忘れようとはしなかった。数ヶ月後、慎也から一通の手紙が届いた。
「遥へ
あのとき、君に本当の気持ちを伝える勇気がなかったことを後悔しています。けれど、君と再会したことで、もう一度自分の人生を見直す決意ができました。これからの道をどう進むべきか、しっかり考えます。君もどうか、自分の幸せを見つけてください。」
手紙を読んだ遥は、涙を流しながら微笑んだ。そして、自分の人生を自分で切り開く決意を新たにした。鏡に映る自分の姿に向かって、静かにこうつぶやいた。
「これからは、自分を大切にしていこう。」
その日から、遥は少しずつ、自分の新しい未来を描き始めた。
0
0
0